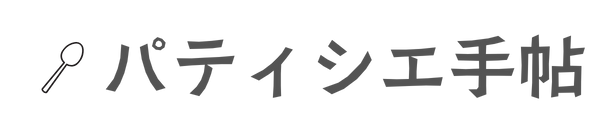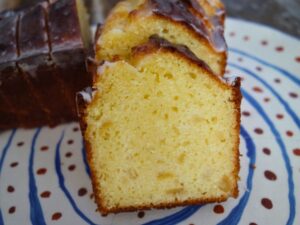マドレーヌはフランスで生まれましたが、今では世界中で同じ形と味わいで親しまれているお菓子となりました。
この記事では、マドレーヌの誕生の由来や発展の歴史、とりわけ有名なコメルシーのマドレーヌについて取り上げます。さらに、ポンペイでマドレーヌ型が発掘されたという伝説や、フランスでは誰もが知る『プルーストのマドレーヌ』についても解説し、マドレーヌがいかにして世界に広まったのか、その物語をたどっていきます。
マドレーヌとは?
マドレーヌは小麦粉や砂糖や蜂蜜、バター、卵を合わせて、貝の形の型で焼いたお菓子です。日本では菊型のものもありますが、フランスでは縦長の貝型が一般的です。
フランス語の名前
- Madeleine
-
[madlɛn] マドレーヌ / フランス語
マドレーヌの構成・材料
| 分類 | パティスリー/プチガトー |
| 構成 | スポンジ生地 |
| 材料 | 小麦粉 卵 バター 砂糖 蜂蜜 レモンの皮 |
マドレーヌが誕生した由来
マドレーヌが作られるようになった由来はいくつかありますが、よく知られた3つを紹介します。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼説
帆立貝はフランス語でサン=ジャック(Saint-Jacques)と言います。サン=ジャックと呼ばれるようになる前は、ラテン語 « pecten » から派生した « peigne » と呼ばれていました。« peigne » は「櫛」という意味で、放射状の縞模様が櫛の歯に似ていることに由来しています。帆立貝がサン=ジャックと呼ばれるようになったのは中世に入ってからです。
中世時代、帆立貝は古代の信仰や慣習に由来する意味をもち、サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Saint-Jacques de Compostelle)巡礼の重要なシンボルとなっていました。また、帆立貝の形はキリスト教の使徒聖ヤコブ(Saint-Jacques)に由来する純潔や愛、神聖な原理と結びついた宗教的なシンボルです。
コンポステーラへの巡礼が行われていた頃、若いマドレーヌという名前の女の子が巡礼者のためにお菓子を振る舞っていました。彼女は信仰のシンボルだった帆立貝を型にして、卵を使ったお菓子を作りました。各地に戻っていく巡礼者によって、このお菓子「マドレーヌ」が広まっていきました。
という、巡礼のシンボルである帆立貝とマドレーヌの形が結びついた説です。
コメルシー誕生説
由来の中でも最も有名で受け継がれているのは、このコメルシーで生まれた説です。
コメルシーとはフランスの東部、現在のグラン・テスト地域圏ムーズ県にある町です。コメルシーの隣町バール=ル=デュック(Bar-le-Duc)という説もあります。
コメルシーで生まれた物語は2つ残っています。
17世紀、レッツ枢機卿であるポール・ド・ゴンディ(Paul de Gondi)がコメルシーに追放されました。地元の貴族を受け入れるために、彼は定期的に城で宴会を開きました。
料理人マドレーヌ・シモニン(Madeleine Simonin)は宴会で何か料理を出したいと考えました。1661年、彼女は揚げ生地を改良してふわふわした小さなケーキを作りました。そのお菓子は招待客にたいへん喜ばれ、彼女の名前から「マドレーヌ」と名付けられました。
もうひとつは、スタニスラス・レクザンスキ王(Stranislas Leczinski)の城で生まれた話です。
ルイ15世が権力を握りフランスが繁栄していた1755年、フランスの東部にロレーヌという公国(Duché de Lorraine)がありました。その公国を治めていたのはルイ15世の妃の父親であるスタニスラスでした。彼は大食漢で美食家としても有名でした。
ある日、彼はコメルシーで宴会を開きました。宴会の途中で料理人とパティシエがケンカをし、最後のデザートを準備せずに出ていきました。そのとき、召使いをしていたマドレーヌ・ポルミエ(Madeleine Paulmier)は祖母から教わっていた生地をホタテの貝殻に入れて焼き、それをデザートとして供しました。
そのデザートを王様は大変気に入り、そのお菓子に彼女の名前である「マドレーヌ」と名付けました。
宴会で起こった喧嘩などの詳細が事実かは不明ですが、コメルシー辺りで考案されたことは有力なようです。
最高級パティシエ考案説
パティシエで歴史家であるピエール・ラカン(Pierre Lacan)1によると、政治家で外交官のタレーラン(Talleyrand)の元に仕えていたジャン・アヴィス(Jean Avice)がカトルカールの生地を帆立貝の生地に入れて焼いたと述べています。
アヴィスは当時最高級のパティシエで、マドレーヌの生みの親とも言われています。
そして、「マドレーヌ」という名前を付けたのは彼の弟子で偉大な菓子職人アントナン・カレーム(Antoine Carême)であるという説もあります。ちなみに、なぜ「マドレーヌ」だったかというと、アヴィスの愛人の名前だったからだったとか…。
19世紀からのマドレーヌの発展
19世紀に入ると、マドレーヌは広く知られていきます。
まず、ブルジョワや貴族に仕えていた料理人やパティシエが新たなマドレーヌのレシピを考案し、晩餐会で提供しました。
美食家グリモ・ド・ラ・レイニエール(Grimod de La Reynière)はクリームやゼリーに添えるお菓子としてマドレーヌを挙げています。カレームはマドレーヌケーキ(Gâteau à la madeleine)や粗糖を塗したマドレーヌなどを考案しました。ジュールズ・グーフェ(Jules Gouffé)はマドレーヌ生地にレモンコンフィやレーズンを加えました。
次に、マドレーヌの商品化が始まり、一般にも広く普及していきます。
18世紀半ばから始まった産業革命により、蒸気機関を用いた製粉所の普及により小麦粉が安定的に生産でき、金属加工技術の発展により焼き型が大量生産されるようになりました。さらに、ビート糖(甜菜から作る砂糖)の普及により、砂糖がより安価に手に入るようになりました。これらの要因により、マドレーヌは工場で大量に作られるようになりました。
1810年代には30サンチームだったマドレーヌは、1840年ごろには15サンチームに値下げされました。価格効果もあり、年間2万個のマドレーヌが生産されました。
家庭でも作られるようになり、マドレーヌ生地をフライパンで焼いていました。
鉄道網の発達により、地方の特産品がパリなどの大都市に運ばれやすくなりました。ロレーヌ地方のコメルシーで作られたマドレーヌは鉄道で首都へ運ばれ、「地方の名物菓子」から「全国的な定番菓子」へと広まりました。
コメルシーのマドレーヌは19世紀前半から人気を博しはじめ、多くの製造業者がいました。そのひとつはドゥブジー=ブレイ家 « Debouzie-Bray » で、マドレーヌをヴォージュ産のモミの木材で作った箱に詰めた商品 « madeleine de La Cloche d’Or » で有名となりました。この箱に描かれている教会の鐘は、スタニスラス王がコメルシー教会を支援していたことに由来しています。この商品は今でも販売されています。(下記リンク参照)

19世紀末から第二次世界大戦のころまで、コメルシーを列車で通過する際、乗客は車両のドアに群がりマドレーヌを買っていました。マドレーヌの売り子は大きな柳のカゴを抱えて、コメルシー駅の人ごみの中を歩き回りながら、自分たちの工場の名前を大声で叫んでいる光景が見られました。
コメルシーのマドレーヌ
コメルシーで考案されたマドレーヌが本家とされ、その後大きく発展していきました。
コメルシーのマドレーヌのレシピ
コメルシーのマドレーヌのレシピははっきりと明らかにされていません。
マドレーヌは卵と砂糖、小麦粉、バターの4つですが、コメルシーでは泡立てた卵白に他の材料を合わせて作るのが特徴と言われています。生地がふわふわに膨らみ軽い食感となります。
また、19世紀には、コメルシーのマドレーヌの大きさについて言及されています。1個の重さは80~100gで、長さ12cmで幅8cm、中央の高さは4cmと記録されています。現在の市販されているマドレーヌ(重さ36g、長さ8cmで幅6cm、高さ3cm)と比べると、かなり大きかったことがわかります。大きさの割にずっしりとした重さだったことが想像できます。
コメルシーのマドレーヌの価格
1810年代にコメルシーのマドレーヌは30サンチームで販売されていたのにも関わらず、非常に人気でよく売れていました。
ヨーロッパではナポレオン体制が崩壊して、ヨーロッパの秩序が再編された19世紀前半、マドレーヌはどのくらいの価値だったのでしょうか。
当時、1フラン=100サンチームで、1フランには純銀5gを含んでいました。
1820年〜40年代のパリの労働者の日給は1,5〜1フランで、パン1kgは30〜40サンチームでした。よって、マドレーヌ1個は非常に贅沢なお菓子だったことがわかります。
実際にはマドレーヌは労働者の中で広まったのではなく、お金持ちのブルジョワの中で広まっていきました。
ポンペイで発掘された伝説
これまでにいくつかのマドレーヌ誕生説をお伝えしましたが、フランスの辞典や本にはもっと古くからマドレーヌは存在していたと思われる文章が出てきます。
Doit on ajouter que la célèbre madeleine d’Illiers était déjà connue au Moyen âge et qu’on a trouvé des moules dits « à madeleine » dans les fouilles de Pompéi ?2
訳: イリエ(Illiers)の有名なマドレーヌは中世に既に知られており、いわゆる「マドレーヌ」の型がポンペイの発掘調査で発見されたことも付け加えるべきだろうか。
Si l’on trouvé des moules en forme de coquilles dans les fouilles de Pompei, l’origine de la madeleine reste controversée.3
訳: ポンペイの発掘で貝殻の形をした型が見つかっているが、マドレーヌの起源は議論が残る。
このふたつの文によると、「マドレーヌはすでに中世では作られていた」「ポンペイ遺跡ではマドレーヌのような型が発見された」と書かれています。これは本当なのでしょうか?
これまでに解説したように、マドレーヌは17~18世紀にコメルシーを中心とする地方で名が広まり、19世紀にパリやブルジョワ社会で定着していきます。
ポンペイで発掘されたのが「マドレーヌ型」とすると、西暦79年頃の古代ローマ時代にはすでにマドレーヌが作られていたということになります。しかし、実際にはポンペイ遺跡では「マドレーヌ型」は発見されていません。貝殻模様の金属型や陶器型の発掘はありましたが、マドレーヌを焼くためだったとは確認されていません。
また、中世のフランスの町イリエでマドレーヌが作られていたというレシピや調理法などの証拠は残っていません。伝承や地方の郷土菓子の系譜にもとづく推測ではないでしょうか。イリエは『失われた時を求めて』でコンブレー(Combray)という町のことで、マドレーヌを表す象徴的な町です。(次章を参照)
実は、フランスの食文化では、しばしば起源の古さを強調する物語が権威づけの引き合いに出されることがあります。たとえば、ワインは「古代ローマ人がすでに葡萄を栽培していた」と語られ、チーズも「ガリア時代からの伝統」として誇られます。パンについても「キリストの時代からの食物」という宗教的な文脈と結びつけられています。マドレーヌも同様に、ポンペイや中世を引き合いに出すことで、ブランドや名声を高め、「もっと古くから存在していた」という物語が好まれるのです。
さらに、前述したように、コンポステーラ巡礼路のシンボルである帆立貝とマドレーヌの型と結びつけ、偉大なパティシエもマドレーヌの発案に大きく関わっているというストーリーは、マドレーヌの宗教的・社会的権威を結びつけることに成功しています。
やがてマドレーヌは、文化的な栄誉と名声に包まれていきます。
プルーストのマドレーヌ
20世紀初頭に書かれたマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』第1巻「スワン家の方へ」にマドレーヌが登場する有名な場面があります。
母親が紅茶とマドレーヌを勧め、語り手が紅茶に浸したマドレーヌを口にする。その瞬間、子ども時代に叔母がくれたマドレーヌの記憶と共に、コンブレーで過ごした日々を思い出した。記憶は断片的ではなく、味覚をきっかけに無意識に眠っていた全体の世界が蘇る。
プルーストはこれを「無意志的記憶」と呼びました。これはフランス文学における「時間」と「記憶」をめぐる最も有名な表現のひとつです。
フランスでは « la madeleine de Proust » « C’est ma madeleine de Proust » という言い回しが日常的に使われます、これは「プルーストのマドレーヌ」「これが私のプルーストのマドレーヌ」という意味で、ちょっとした匂いや味などをきっかけに、強烈に過去の記憶が蘇る体験のことを指します。
例えば、« Cette chanson est ma madeleine de Proust. »(この歌を聞くと一気に昔を思い出す)というように使います。また、学校の卒業アルバムやタイムカプセルはその当時への郷愁を抱かせる「プルーストのマドレーヌ」だと言われます。
さらには、映画にもしばしば登場します。例えば、2007年公開のアニメ映画『レミーのおいしいレストラン』では、料理評論家がラタトゥイユを食べて子ども時代の記憶に一気に戻される場面があります。これは典型的な「プルーストのマドレーヌ」のオマージュとして表現されています。
このように何かをきっかけに過去がフラッシュバックする演出は「プルースト的瞬間」と呼ばれ、国際的に定着しています。
ここで話をマドレーヌに戻します。マドレーヌは近世に作られた単なる地方菓子のひとつにすぎませんでした。19世紀には権威的な物語が加わり、マドレーヌは確固たる地位を得ました。
そして、20世紀に入り、プルーストの小説によって 「個人的な味覚の記憶が、普遍的な時間と存在の探求に結びつく」 象徴になったのです。
つまり、フランス人の幼少期や故郷、家庭の古い記憶と普遍的な文学的モチーフを具現する存在となりました。こうして、マドレーヌは考古学的・宗教的・社会的な物語に加えて、フランス文化の永遠性や普遍性といったものを象徴するイメージとなり、フランスを代表するお菓子のひとつとなりました。その豊かな魅力は今でも続いており、世界中で愛されています。
調べれは調べるほど伝えたいことがたくさんあり、長い話になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。マドレーヌを味わう際には、これらの物語を思い出していただければ嬉しいです。
最後に、あなたにとってのプルーストのマドレーヌは何ですか?
- Dictionnaire de la gourmandise: Pâtisseries, friandises et autres douceurs
- La merveilleuse histoire des pâtisseries
- Mots de table, mots de bouche Dictionnaire du vocabulaire classique de la cuisine et de la gastronomie
- À La Cloche Lorraine Madeleine de Commercy
- 失われた時を求めて
- レミーのおいしいレストラン
- Madeleine de Proust : Signification et origine
- Illiers-Combray
- Pourquoi les coquilles Saint-Jacques s’appellent-elles ainsi ?
- Pierre Lacam, Le Mémorial historique et géographique de la pâtisserie, contenant 1,600 recettes de pâtisseries: glaces et liqueurs, Hachette Livre BNF, 2017. ↩︎
- Claudine Brécourt-Villars, Mots de table, mots de bouche Dictionnaire du vocabulaire classique de la cuisine et de la gastronomie, La Table Ronde, 2023. ↩︎
- Annie Perrier-Robert, Dictionnaire de la gourmandise: Pâtisseries, friandises et autres douceurs, Bouquins, 2012. ↩︎