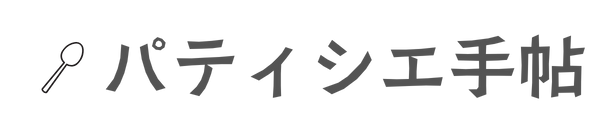今回は、フランスのアルザス地方で有名なお菓子クグロフについて紹介します。クグロフは有名なお菓子なので、伝説級の話、マリー・アントワネットやカレームなどの有名な人物も関わってきます。
この記事では、フランス語の名前の由来やバリエーション、クグロフ型、歴史、クグロフから発展したお菓子について、フランスの辞書や本を参考にして書きました。クグロフについてすべてのことが分かるようになるはずです!

クグロフとは?
発酵生地でつくったブリオッシュにレーズンを混ぜて、アーモンドを表面に飾り、縦溝のある王冠型で焼いたお菓子のことです。
フランスの東部アルザス地方で伝統的に作られており、スフレンアイム村の陶器製のクグロフ型が有名です。
材料・構成
| 分類 | パティスリー/ガトー |
| 構成 | 発酵パン生地/クグロフ生地 |
| 材料 | 小麦粉 卵 バター 砂糖 酵母 ドライレーズン アーモンド |
フランス語の名前
- kouglof / Kougelhopf
-
[kuɡlɔf] クグロフ / フランス語
- Napfkuchen
-
[nap͡fˌkuːx] ナップクーヘン / ドイツ語
kuchenは「菓子」という意味
名前のバリエーション
上記にクグロフの綴りを書きましたが、これ以外にもたくさんの綴り、国や地方によって異なります。
Kugelhopf / Gugelhopf / Kougelhopf / kougelhof / Kouglof / Kugloff / Kugelhupf / Gougelhof / Gougelhopf / Gugelhoph / Guglhupf / Gougloff / Cougloff
クグロフの名前の由来
Kugelhopf の場合、「球」を意味する « kugel » と「ビール酵母」の « hopf » に由来していると言われています。
Gugelhopf の場合、中世時代の僧侶の頭巾 « gugel » がクグロフの形に似ていること、「酵母」を意味する « hopf » に由来している説もあります。
ドイツのプファルツ地方では「トルコの帽子」、オランダでは「ターバン」とも呼ばれており、クグロフが帽子(フード)の形に似ていることからその名前がつけられたことが分かります。
しかし、クグロフほど有名なお菓子の名前がこんな単純な由来だけで終わるはずがありません。(のちの「歴史」の項に続きます)

クグロフの型
クグロフは縦溝のある王冠形で、中央に穴があいている型で焼いているのが特徴です。型の中央の穴は煙突状になっており、生地中心の熱を逃すためにあるもので、この機能はローマ時代から知られていました。
クグロフ型はストラスブールの近くにあるスフレンアイム村(Soufflenheim)で作られる陶器の型が有名です。
スフレンアイム村の陶器の歴史
1142年、スフレンアイム村で本格的に陶器作りが始まりました。というのも、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(1122-1190)が職人に近くのアグノー(Haguenau)の森から粘土を無償で採取する権利を与えたのです。
ある伝説では、森で狩りをしていたフリードリヒ1世が猪に襲われたところを地元の陶工が間一髪のところで助け、この勇気を称えたことがきっかけだという話もあります。
スフレンアイム村の住民は「ヘレガイシュター « Hellegeischter »」と呼ばれていました。これは「地獄の霊」という意味です。
どうしてこんな怖い呼び名がついたのかというと、陶工が用いていた薪窯に由来します。薪窯の炉が最高温度に達すると、高い煙突から煙と炎が吹き出します。特に、夜中に吹き出す炎と煙の渦は、まるで地獄の業火の如き光景でした。この恐ろしい場面から「地獄の霊」という呼び名がつけられました。
スフレンハイム村では当時からエルヒンガー家(1834-2016)やジークフリート家(1811-2019)などの有名な家族が輩出されました。1970年代まで30人ほどの陶工に支えられ、最大1500人の雇用を生み出しました。
しかし、21世紀に入ると、安価なアジア製品が台頭し、この村の多くの職人が廃業を余儀なくされました。近年では本物の職人技への関心が再び高まり、スフレンハイム村の陶器は脚光を浴びています。
スフレンハイム村ではクグロフ型ではなく、ベッコフ(ジャガイモと豚肉を使った煮込み料理)やアニョー型などさまざまな陶器が製作されています。
クグロフの歴史
おそらくクグロフが初めに作られたのは、ドイツ南部ではないかと言われています。オーストリアやドイツのライン地方では18世紀に知られるようになり、アルザスやポーランドでもその存在は知られていました。クグロフは結婚式や洗礼式といったハレの日に食べられていました。
有名なお菓子には必ずといっていいほど、すばらしい伝説が残されています。
アルザスで伝説が作られる
アルザスでは18世紀半ばにクグロフが知られるようになりました。アルザスでは「東方の三博士」に関する2つの伝説が残っています。
一つ目はクグロフの綴りのひとつ « Kugelhopf »という名前のお菓子が誕生した伝説です。« Kugelhopf » はストラスブールの近くの村リボーヴィレ(Ribeauvillé)が発祥とされており、クグロフ型とも深い関係があります。
物語は今から2000年以上前に遡ります。西暦4年にベツレヘムでイエス・キリストが誕生した頃、リボーヴィレ村にクーゲル(Kugel)という名前の陶工が住んでいました。
ある冬の夜、3人の著名な外国人がクーゲルの家を訪れ、宿を提供してほしいと頼みました。もてなしの習慣に従い、彼は自分のアトリエ兼居間に3人を招き入れ、食事と宿を提供しました。
この3人は幼子キリストを礼拝した後にケルンに向かう途中の東方の三博士でした。クーゲルの厚遇に感謝した博士たちは、甘いお菓子とそれを焼くための型を作ることにしました。彼らは粘土で山の形の型を作り、お菓子の生地も準備しました。焼き上がったお菓子はヴォージュ山脈の雪に覆われたオネック山(Hohneck)のように美しく、仕上げに振りかけた粉糖は山に積もる雪のようでした。

二つ目の伝説も同じように、リボーヴィレ村のクーゲル陶工が登場します。その前に、少しこのアルザス地方の歴史の話をしたいと思います。
11世紀からアルザス地方はシュヴァーベン公国の領地でした。この公国を支配した有力な一族がホーエンシュタフェン家で、1079年から1208年にかけてのほとんどの間、同家は神聖ローマ皇帝をかねていました。1152年、同家のコンラート3世が亡くなると、フリードリヒ・バルロッサ国王(のちの神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世)が選出されました。フリードリヒ1世はおそらくリボーヴィレ村近郊のアグノー村で生まれたとされています。よって、アルザスやライン川両岸の住民にとって、彼は神聖ローマ皇帝というよりも「地元」の君主という認識でした。
1162年、フリードリヒ1世はイタリアのミラノへ軍事遠征を始めます。彼らはミラノの宗教施設は破壊しませんでしたが、略奪行為を行いました。ミラノには多くの聖遺物が安置されており、中でも東方三博士のものが有名でした。1162年6月11日、フリードリヒ1世は「計り知れない、数えきれないほどの奉仕」に対する感謝として、皇帝の支持者であるケルン司教にこの東方三博士の聖遺物を授与することにしました。
ケルン司教はこの聖遺物をミラノからケルンに運ぶ使命を務めました。ケルン司教は道中リボーヴィレ村に立ち寄ります。この村のクーゲル陶工(Kugel)はケルン司教を厚くもてなしました。
この伝説から、クーゲルと名前のついたお菓子を考案し、これがクグロフの誕生です。
どちらの伝説もクーゲル陶工は登場するし、舞台はリボーヴィレ村です。実際に東方三博士、もしくは彼らの聖遺物がアルザスを訪れたのかもしれません。それを証明するように、ストラスブールやコルマールなどの美術館には東方三博士の礼拝のシーンを描いた絵画が多く展示されています。
アントワネットが夢中になる
クグロフのようなお菓子はポーランドでも食べられており、スタニスラス王も好んでいました。ロレーヌ公に就いた際に、このお菓子はポーランド人パティシエによってロレーヌ地方へもたらされたといわれています。
この「クグロフのようなお菓子」はポーランドのバブカだとされています。クグロフとバブカはほぼ同じお菓子です。
スタニスラス王の娘マリー・レクザンスカはルイ15世の妃であり、彼女の元へもクグロフのようなお菓子が届けられていたのではないかと想像できます。
オーストリアのハスプブルグ出身のマリー・アントワネットも大好きで、小さい頃から親しんでいました。彼女とルイ16世の婚姻により、フランス宮廷にクグロフが広まりました。アントワネットは午前中にカフェとクグロフを食べるのが気に入っていました。ヴェルサイユ宮殿にクグロフを紹介し、同時にパリでも流行らせたのはアントワネットだとしています。
アントワネットの有名な言葉「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」というのがありますが、この「お菓子」はクグロフを指していると言われています。






パリで普及する
19世紀に入り、偉大なパティシエであるアントナン・カレームが登場します。彼もまたクグロフを有名にした人物のひとりです。
カレームは1810年のナポレオン1世の結婚式の際に、ウジェーヌ(Eugène)によりレシピを教えてもらいました。ウジェーヌはドイツの貴族シュヴァルツェンベルグの王子(オーストリアの外交官)の料理人でした。
実際、カレームのメニューの中のデザートに、「ウィーン風クグロフ(Cougloffe à la viennoise)」と書かれていました。
1840年のピエール・ラカンの『菓子製造業の覚書』には、「パリのコック=サン=トノレ通り1(Rue du Coq-Saint-Honoré)にあるパティスリーのジョルジュ(George)という菓子職人がストラスブールからのレシピをもとにクグロフを製造している」と書かれてあります。
パリでもクグロフが流行し、毎日100個も売れていました。ジョルジュは25人の職人を雇っており、その店の小僧(若い職人)たちは « Kugelmann(クーゲルマン)» と呼ばれていました。
そのレシピは「たっぷりのバターとマラガ産のレーズンを加え、鐘形の陶器の型を使う。型の内側にはバターを塗り、アーモンドスライスを貼り付け、焼き上がったら粉糖を振りかける」とされています。この作りかたは今のものとまったく同じです。
19世紀半ばに活躍したシェフ兼パティシエであるジュールズ・グーフェ(Jules Gouffé)は「ウィーン風クグロフとポーランド風クグロフは別物であり、前者にはアーモンドや干しぶどうが入っていない」と述べています。この時代にはすでにいくつかの種類のクグロフが登場し、分類が必要なほどだったことが分かります。
- 現在のリヴォリ通り(Rue de Rivoli) ↩︎