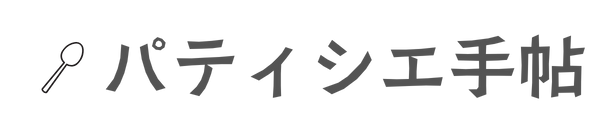今回は、フランスでも人気で定番のデザートであるババオラムを紹介します。フランスでの現状もお伝えしつつ、ババオラムの構成や材料、バブカやクグロフからは派生したババオラムの歴史や由来を解説しています。また、サヴァランとの違いも取り上げています。
この記事でババオラムのすべてがはっきりと分かるようになるはずです。
ババオラムとは?
ババオラムとは、発酵パン生地を円柱や丸い型で焼き、ラム酒で香り付けした熱いシロップを染み込ませたお菓子のことです。レストランではホイップクリームを添えて提供されることがあります。
フランスのレストランのデザートでは、ババオラムが提供される際、ラム酒のボトルが添えられてくることがあります。特に、リヨンのレストラン(ボール・ボキューズのブラッスリーなど)ではよく見かけます。
ラム酒入りのシロップにはすでに漬けてあるのですが、さらに好みでラム酒を振りかけることができます。ボトルと共にデザートが登場してきてテンションが上がるのはわたしだけではないはずです。
ラム酒のアルコール度数は40%ほどなので、流石に食後のデザートとしては重すぎでは?と思うかもしれませんが、ババの甘さと相まってさらに美味しくなります。

フランスの製菓辞書(Dictionnaire de la gourmandise / Dictionnaire FERRANDI)によると、ババには干しぶどうを加えると記してあります。しかし、実際、フランスのパティスリーやレストランで提供されるババオラムは干しぶどうは加えていません。また、レシピでも干しぶどうを加えることはありません。
以前は干しぶどうを加えることが一般的だったのですが、現在では好みが変わってしまったのかもしれません。
そして、フルーツコンフィやドライフルーツを飾るということも辞書に書かれてあります。現在ではあまり見られませんが、実際に2006年ごろフルーツコンフィが添えられたババオラムがありました。

フランス語の名前
- Baba au rhum
-
[babaoʁɔm] ババ オ ロム / フランス語
« rhum » はリキュール「ラム酒」のことで、「ラム酒風味のババ」という意味
ババオラムの構成・材料
| 分類 | パティスリー/デザート |
| 構成 | 発酵パン生地/ブリオッシュ生地/ババ生地 ラム酒入りのシロップ シャンティイクリーム |
| 材料 | 小麦粉 卵 バター 砂糖 酵母 生クリーム ラム酒 |
ババオラムが誕生した由来
ババはスタニスラス・レクザンスキ王が案を出したお菓子のひとつです。スタニスラス・レクチンスキとはポーランドの王様およびロレーヌ公で、ルイ15世の妃マリーの父親です。
1736年、スタニスラス王はフランスへ亡命し、ロレーヌ公国の王となり、ナンシーの近くにあるリュネヴィル城に移住しました。
スタニスラス王は食いしん坊な王様として有名で、料理やお菓子についても詳しい知識を持っていました。
ババオラムが生まれた説はいくつかあり、どちらも似たような話ですが、「バブカ由来」「クグロフ由来」のふたつが有力です。
バブカから生まれた説
スタニスラス王は小さい頃から母国ポーランドで食べていたブリオッシュが大好きでした。そのブリオッシュとはポーランド語でバブカといい、丸くて大きく王冠の形をしていて、中身にはきざんだドライフルーツがちりばめられ、レモンで香りつけされたお菓子でした。
バブカとはポーランド語で「老婆」や「おばあちゃん」という意味があり、スタニスラス王にとってもおばあちゃんの味でとても懐かしかったのでしょう。
そのお菓子の味が忘れられなかった王は、ポーランドからそのバブカを運んできてもらいました。しかし、その当時は発達した輸送手段はありませんので、当然長時間移動してきたバブカは乾燥してしまいます。
スタニスラス王の娘マリーはフランス王ルイ15世に嫁ぎ、ベルサイユ宮殿で暮らしていました。スタニスラス王は娘のパティシエであるニコラ・ストレーに、この乾燥してしまったお菓子をなんとか美味しくする方法を相談しました。
ストレーはバブカをマラガワインに漬け、中にカスタードクリームとギリシャ産のドライレーズンをはさんで冷たく冷やしたお菓子を作りました。このお菓子が作られたのは1725年〜30年とされています。
さらに美味しくなるように改良していき、マラガワインをラム酒、クレーム・パティシエールをシャンティイクリームに変えました。
クグロフから生まれた説
1609年からランベルグ(Lemberg)でクグロフ(Kugelhopf)が作られていました。
これをスタニスラス王は食べたとき、乾燥しすぎていると感じ、もっと美味しくするためにシロップに漬すというアイデアを思いつきました。
王はパティシエのストレーに相談し、ストレーはラム酒で香りをつけるアイデアを提案しました。焼いた生地を型から外してラム酒を振りかけ、風味を凝縮させるために布に包みました。
このラム酒入りのシロップに漬けたお菓子は宮廷で大きな評判を呼びました。
以上、2つの説があります。クグロフとバブカは地域によって名前が異なるだけで同じお菓子です。フランスの本や辞書によって話が微妙に違ったりします。

ババの名前の由来
スタニスラス王はこの新しくなったお菓子にとても満足して、「アリババ」と名付けました。当時、流行していて王も愛読していた「千夜一夜物語」の登場人物の名前に由来しています。
その後、ストレーは自身のパティスリーで「アリババ」を作り、「ババ」と短縮して名付けました。ここで、ようやく「ババ」という名前となり、ラム酒を加えていたことから「ババオラム(ラム酒風味のババ)」が完成しました。
また、1767年、ディドロ(Diderot)によると、「老婆」を意味する « baba » に由来しているともいわれています。
どちらの説もスタニスラス王がポーランドからこのお菓子を持ってきて、改良を加えたということを仄めかしていますね。
パリでババオラムが広まる
パリでババを広めたのはストレーです。
ニコラ・ストレーはスタニスラス王のリュネヴィル城でパティシエのキャリアを始めました。1725年、スタニスラス王の娘マリーがルイ15世と結婚した際に、ヴェルサイユ宮殿へ移り、マリーのパティシエとなります。
その後、1730年に宮殿を去り、パリに自分のパティスリーを開きます。パリ2区のモントルグイユ通りにあるストレー(STOHRER)で、現在でも営業しているパリで最も古いパティスリーです。その店でのスペシャリテがババオラムとなりました。
ストレーがババにラム酒シロップを染み込ませたことで、名前が「ババオラム(Baba au rhum)」という名前になりました。

ババオラムとサヴァランの違い
ババオラムとサヴァランって似てるようなお菓子ですが、どこが違うの?っていう質問がよくあります。
ババオラムとサヴァランて似たようなお菓子ですよね。それもそのはずで、サヴァランはババオラムから生まれました。
似ているお菓子の違いをはっきりさせるのは正直難しく、時代や作り手などの要因で定義が変わってきたりします。今回は、材料、形、飾り、シロップという観点で調べてみました。
- 材料
-
材料はどちらも同じ材料の発酵パン生地を使っています。辞書によると(上記参照)ババオラムに干しぶどうを加えるとされていますが、今では入っていることはあまりありません。想像ですが、シロップが十分に甘いので、干しぶどうで甘さを加える必要がなくなったからでは?と考えています。
- 型・形
-
一般的にババオラムは円柱状の型をつかい、サヴァランはドーナツ状の王冠型をつかいます。しかし、形はこの限りではなく、ババオラムが長方体だったり、王冠の形だったりします。なので、形だけでは判断できません。
- 飾り
-
定義によると、ババオラムはクリームなどは加えませんが、実際にはホイップクリームが添えられていることが多いです。場合によってはフルーツやバニラアイスクリームが添えられていることもあります。サヴァランはクリームかフルーツが必ず添えられます。なので、飾りにはっきりとした違いはありません。
- シロップ
-
ババオラムにはラム酒を加えたシロップに染み込ませています。サヴァランもシロップに漬けますが、ラム酒は必ずしも必要ではありません。ババオラムはその名前の通り、ラム酒が必須です。
よって、ババオラムとサヴァランの違いは、ラム酒の有無で、ラム酒が使われているのがババオラムで、使われていないのがサヴァランと言えます。









ババオラムに関連するお菓子
参考文献
この記事を書くために参考にした本です。