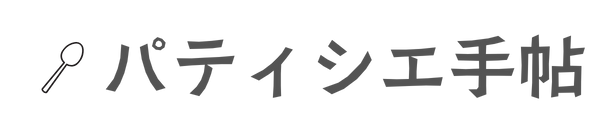お菓子とキリスト教の祝日はとても密接な関係があります。昔、民衆を異教からキリスト教に改宗させるために、お菓子を食べる習慣を利用しました。
フランスの祝祭日とキリスト教の行事、それらに関係するお菓子をまとめました。
フランスの祝日は主にキリスト教や戦争に関係するものがみられます。
1月1日:元旦
1月1日は元旦で、フランス語ではJour de l’an(ジュール・ド・ラン)と言います。1月1日は祝日ですが、翌日の2日からは通常の平日となります。大晦日の夜に花火が上がる町もあり、大晦日と元旦はお祭りの雰囲気があります。
大晦日の夜は家族で過ごすというよりも、友人や恋人とお祝いをすることの方が多いように感じます。
大晦日や元旦に食べるお菓子や料理は特に決まっていません。レストランやパティスリーも閉まっていることが多いです。
1月6日:公現祭(エピファニー)
エピファニー(Épiphanie)は1月6日のキリスト教の祝日で、東方から来た三博士がイエス・キリストの生誕を祝い礼拝した日です。日本では主顕節や公現節と言います。
旧典礼暦では1月6日ですが、現在では1月2日〜8日の間の日曜日に設定されます。祝日にはなりません。
聖書によると、3人の博士が東方で巨大な赤い星を見つけました。それは救世主の生まれたしるしであるという言い伝えにより、彼らはラクダに乗って星を追い続けました。すると、12日目の1月6日にベツヘルムの馬小屋の真上で星はとまりました。3人の博士はイエス・キリストの誕生にまみえ、黄金・乳香・没薬を贈りものとしてささげました。これにより主の誕生が人々に知られることになりました。
エピファニーにはフェーブを詰めたガレットデロワやガトーデロワを食べる習慣があります。クリスマス時期が終わるとすぐにガレットデロワやガトーデロワがパティスリーなどに並び始め、1月末まで続きます。
2月2日:聖燭祭(シャンドルール)
聖燭祭はフランスではシャンドルール(Chandeleur)と言い、はキリスト誕生の40日後に聖母マリアが清めのために神殿に詣でたことを祝う日です。「聖母マリアのお清めの日」とも言います。
この日にはクレープを焼いて食べるという習慣があります。丸くて黄金色のクレープは太陽を象徴しており、春の到来を願って作られています。
また、南仏の街マルセイユではナヴェットを食べる習慣があるそうです。
2月14日:聖バレンタイン
聖バレンタイン(Saint-Valentin)は3世紀にローマ皇帝のクラウディウス2世の結婚禁止令を無視し、兵を結婚させた司祭ヴァランタンが処刑された日に由来します。
2月14日のバレンタインデーは日本でも馴染みのあるイベントです。
チョコレートを贈るという習慣はイギリスのカドバリー社が始め、日本では女性がチョコレートを贈る習慣があります。フランスでは恋人やカップルが花やチョコレートを贈り合ったり、レストランへ食事に行くことが多いようです。
2月:謝肉祭(カーニバル)
謝肉祭(カーニバル)はキリスト教の摂食の期間である四旬節を前に、たくさん食べて大騒ぎしておこうというお祭りのことです。移動祝祭日で、2月頃に行われます。フランス語ではカルナヴァル(Carnaval)と言います。
地域によって異なりますが、1週間程度続きます。地方ごとにさまざまな揚げ菓子を作り、肉などのご馳走を食べます。
2月頃:肥沃な火曜日(マルディグラ)
肥沃な火曜日はマルディグラ(Mardi gras)と言い、カーニバルの最終日の火曜日のことです。カーニバルの最終日で、翌日からは節食がはじまるため、この日ががもっとも盛り上がります。
カーニバルから復活祭までの祭日は2月から4月にあり、固定の日程ではなく毎年日にちが変わる移動祝祭日です。
マルディグラが終わると摂食の期間である四旬節が始まります。節食中は肉などを食べることが禁止されました。この節食に備えるため、カーニバルの期間中に食べ貯めておく習わしがありました。ビューニュなどの揚げ菓子を食べる習慣あり、現在でもその習慣が残っています。
4月1日:エイプリルフール(ポワソンダブリル)
ポワソンダブリルはフランス語で「4月の魚」という意味で、エイプリルフールのことです。フランス王シャルル9世が1564年に1年の始まりを4月1日から1月1日に変更したため、4月1日に偽物のプレゼントをしたのが始まりと言われています。
魚の形をしたチョコレートやお菓子が店頭に並ぶことがあります。
3月〜4月:四旬節(カレーム)
四旬節は灰の水曜日(マルディグラの翌日)から復活祭までの40日間の肉断ちと節食の期間のことです。本来は46日間ですが、日曜日は休息日のためカウントせず40日となります。
四旬節はフランスではカレーム(Carême)と言います。
もともとは肉や卵を食べてはいけない厳しい規則がありましたが、中世以降になると野菜や卵、油や鴨肉が許されるようになり、衣をつけて揚げた料理を食べるようになりました。
3月下旬〜4月下旬 復活祭
復活祭は弟子のひとりに裏切られ十字架にかけられて処刑されたキリストが、3日後に復活したのを祝う日です。フランスではパック(Pâques)と言い、イースターのことです。
四旬節がはじまって40日経った春分後の最初の満月の次の日曜日におこなわれる移動祝祭日で、3月〜4月ごろに行われます。日曜日が復活祭の当日で、翌月曜日も休日となります。
キリスト教の行事の中でもっとも重要な祭日で、卵は生命の誕生、うさぎは子供をたくさん産むため豊かな生命の象徴とされています。
昔は四旬節に貯まった卵を消費するために、卵を大量につかうお菓子や料理を作りました。余った卵の殻は絵を描いたりして飾りに使います。現在では卵やうさぎ、鶏の形をしたチョコレートが定番で、パティスリーやスーパーにたくさん並んでいます。
この時期はクリスマスに匹敵するほどチョコレートが売れる時期になります。また、地方によって作られるお菓子もさまざまあります。アルザス地方ではアニョーパスカルという羊の形をした焼き菓子を食べる習慣があります。
また、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地方の町ロマン=シュル=イゼールあたりではポーニュ・ド・ロマンという王冠型のブリオッシュを食べる習慣がありました。
5月1日:すずらんの日(メーデー)
メーデーは労働者の祭典で、祝日となっており、パティスリーなどの店や交通公共機関なども閉まります。また、フランスではすずらんの日でもあり、愛する人にすずらんを贈る習慣があります。すずらんは春が来たことを知らせる花で、古代より春のシンボルで、幸せを呼ぶ花とされていました。
1561年5月1日、シャルル9世は幸運をもたらすとして贈られたすずらんをたいへん気に入りました。それら毎年同じ日にすずらんをご婦人たちに贈るようになりました。19世紀末になると、庶民もすずらんを贈り合うようになりました。
この日を祝うお菓子は特にありませんが、すずらんや春をイメージするお菓子やチョコレートが店頭に並びます。
5月8日:第二次世界大戦戦勝記念日(Fête de la Victoire)
フランスは第二次世界大戦の戦勝国であり、終戦記念日は祝日となります。
5月頃:昇天祭(Ascension)
昇天祭は復活したキリストが天に昇ったことを記念する日で、永遠の命を象徴します。復活祭から40日後の木曜日に当たり、祝日となります。
5月は前述の5月8日(第二次世界大戦戦勝記念日)と昇天祭と祝日が多く、その祝日と週末の間の平日を有休にして連休にして、プチバカンスを取ることがあります。例えば、5月8日が木曜日だとすると、金曜日に有給を取り、4連休にします。そのことを「フェール ル ポン « faire le pont »」といい、祝日に挟まれた日を休みにすることを意味します。
5月下旬〜6月上旬:精霊降臨祭(パントコート)
精霊降臨祭はフランス語でパントコート(Pentecôte)といい、キリストが復活したあと、弟子たちのもとへ精霊が降りた日のことです。復活祭の7週間後の日曜日にあたり、翌日の月曜も休日となります。
精霊を象徴する白いハトをモチーフとしたコロンビエというお菓子を食べる地域もあります。
7月14日:フランス革命記念日(Fête nationale/14 Juillet)
フランス革命記念日は「国の祭日」のことで、キャトルズ・ジュイエ(Quatorze Juillet)と一般的に呼ばれています。日本では「パリ祭」「フランス革命記念日」と言います。
この日は祝日となり、午前中にはシャンゼリゼ通りで軍隊のパレードが行われ、夜には各地で花火が上がり、消防隊員のパーティなど華やかなイベントが行われます。
この日を境に夏のバカンスの雰囲気が出てきて、国中が動かなくなります。
8月15日:聖母被昇天の祝日(Assomption)
聖母マリアが人生の終わりに、肉体と霊魂を伴って天国にあげられたということを記念する日のことで、祝日となります。
10月31日:ハローウィン(Halloween)
ハローウィンは元々は古代ケルト人が悪魔を崇拝し、生贄を捧げる祭りでしたが、今では宗教的な意味はなくなっています。
フランスでも徐々にハローウィンのイベントが広まっているように感じます。
かぼちゃの中身をくり抜いてジャック・オー・ランタンを作ったり、子供たちはお化けや魔女の仮装をしてお菓子をもらいに行く習慣があります。この時のお菓子はボンボン(bonbon)といい、キャンディやグミ、キャラメル、チョコレートなどの小さなお菓子のことを指します。
11月1日:諸聖人の日(Toussaint)
キリスト教では365日すべてに守護聖人が割り振られていますが、11月1日は全ての聖人を祝う日となっており、祝日となります。フランス語でトゥサン(Toussaint)と言います。翌11月2日は死者の日となっており、お墓参りに出かける習慣があります。
パリ近郊のプロヴァンでは二フレット、南フランスではパヌレというように地域によって作られるお菓子が様々あります。
11月11日:第一次世界大戦休戦記念日
ドイツ降伏と第1次世界大戦終結を記念する日で、今では戦没兵士を追悼する日となっており、法定休日です。
11月末〜12月24日:待降節(Avent)
待降節はアドベント(Avent)といい、イエス・キリストの誕生を待ち望む期間のことです。12月25日から数えて4週前の日曜日から始まり、12月24日まで続きます。
クリスマスはフランスの人々にとって大切な行事で、12月に入ると町中がクリスマス一色となります。11月末からクリスマスまでの間に、アドベントカレンダーやチョコレートが店頭にたくさん並びます。
アルザス地方ではベラヴェッカやノネットといったスパイスの効いたお菓子、クリスマス時期のサブレであるブレデルが食べられています。パンデピスもクリスマスの定番のお菓子で、シュトーレンも全国的に見られるようになりました。トリュフやパピヨットなどのボンボンショコラも欠かせません。さらに、ステッキの形をしたシュクル・ドルジュはクリスマスをイメージするお菓子です。
12月6日:聖ニコラの日(Saint-Nicolas)
12月6日は聖人ニコラを祝う日のことで、ベルギー、ルクセンブルグ、ドイツ、オーストリア、スイス、アルザスを中心とするフランス北東部で祝われています。この聖人ニコラはサン=ニコラ(Saint-Nicolas)とフランス語で言います。
その昔、ニコラが子供たちを助けたという伝説に由来しており、聖人ニコラはこどもの守護聖人として崇められています。12月5日の夜から6日にかけて、子どもたちは聖人ニコラのロバにえさを与えるために、靴下に干し草とオート麦のパンをいっぱいに詰めて煙突にぶら下げました。
これがクリスマスに枕元に靴下を置いておく由来となっています。4世紀には聖人ニコラの形を模したアニス風味のビスキュイやパンデピスで祝っていました。
聖人ニコラはサンタクロースのモデルになっている人物のことで、パンデピスにサンタクロースをアイシングで描いています。また、アルザス地方ではマナラという人の形をしたブリオッシュを食べて祝う習慣があります。
12月25日:クリスマス(Noël)
12月25日のクリスマス(Noël)は1年でもっとも大切なイベントで、24日夜には家族でご馳走を食べる機会です。25日は祝日となり、パティスリーなどほとんどの店や観光施設が閉まります。
フォワグラやスモークサーモン、牡蠣などの海の幸、七面鳥のローストなどが定番の食事です。クリスマスの定番ケーキは薪の形をしたビュッシュ・ド・ノエルがあり、南フランスではトレーズ・デセールという13種類のお菓子を食べる伝統もあります。
クリスマス当日だけでなく、11月下旬からのクリスマスを感じる時期に食べるお菓子としては、プレデルやベラベッカ、スペキュロス、パピヨット、ノネット、シュトーレンなどがあります。イタリア由来のパネットーネもクリスマス時期によく食べられます。